再開発にどこかしらからの資本が入った、と言うが、それを立証するかのように工事をしていたり、路上パフォーマンスなんかもあったりして、土曜の昼間に相応しい活況を呈する駅前付近。俺とセイバーはその中を進み、ヴェルデの入り口に辿り着いた。
「……うわ」
「おお、ここも」
……が、ちょっとひと段落、とはならず。
パッと見ただけで、ヴェルデ内もも相当の人手であることが分かる。
「……なるほど」
「?」
「いや、さっきのトークショー、ここの3階が会場らしい」
時間的にもあと十分。パッと見た感じ、人数制限はやってないようなので、人も集まってくるだろう。
ということは、さっさと目的地に向かった方がいい、ということである。トークショーがスタートすれば、人波も少しはマシになるはずだ。ゆっくりするのは、その後でも構わない。
「ほう、クリスマスツリーですね」
「今はどこも早いからなー」

広場の真ん中には、堂々ともみの木が天に向かって屹立している。飾りはシンプルに淡色の電飾だが、ごてごてしていなくていい、という見方も出来るだろう。
「ま、取り敢えず、チラシ貰っていこうか」
色々差し込んであるチラシの棚から、目当てのものを一枚抜き取る。家に忘れてきたものと同じ、陶器市の広告である。
「呉服、陶器市……」
「ああ。ウチにあったチラシにもあったんだけど……って、あれ」
「どうしました?」
「いや、この屋号……確か、」
チラシの右下隅には、見覚えのある文字が載っていた。
えいどりあ……ではなく、詠鳥庵(えいちょうあん)。昨日は見落としていたが、確か、これは――
「蒔寺の実家だよな、コレ」
「楓のですか?」
「ああ。歴史ある呉服商人の家だからな」
「ほう……?」
ちょこん、と、セイバーが首を傾げている。呉服という知識はあるはずだが、それと蒔寺が繋がらないらしい。
「楓と和装、ですか。んー……」
「想像できない?」
「え? あ、ああ! ち、違うのですよ? 意外だとかそういうのではなくてですね」
……意外、だったらしい。まあ、その反応は真っ当だろう。俺も最初聞いた時は驚いたもんだ。ちなみに、呉服だけでなく陶磁器も扱っていると聞いている。ハイブリッドのような企画売り出しも頷ける、というところ。
「家でも和服だったりするらしいぞ」
「なるほど……。一度、見てみたいものですね」
「確かに。じゃ、行こうか」
エレベーターで上がってすぐ、7階催事場が会場だ。これも何かの縁、というやつだろうか。とにもかくにも、いいものがあればそれに越したことは無い。
「B級……とありますが、どういう意味なのでしょう?」
エレベーター中、セイバーが聞いてくる。エレベーターもまたそこそこの人口密度を誇っていたが、鮨詰めというほどではない。なので、こうして会話を交わすことも出来ていた。
「んー、どう言ったらいいかな」
セイバーはチラシを見て疑問を浮かべている。確かに、チラシにはB級反物、陶器云々と書いてあるので、そう思うのも無理は無い。
「呉服とかだと、ほんの少し縫い違いがあったりしても価値が下がるんだよ。けど、捨てるのもあまりにも勿体無い。そういうのをB級品って言って、安く売るんだ。パッと見だと純正品と変わらないから、お値打ちで手に入れるチャンス、ってわけ」
「なるほど」
陶器なんかでは気に入らない出来だと割ってしまう窯もあるらしいが、市販に回ってくるようなレベルではB級で十分、と言ったところ。Bと自称するだけに値段もそこそこ安くなってるわけで、現にチラシにも「千、二千、三千均一」なんて書いてある。
あとは、セイバーと俺の好みにあった品揃えがあるかどうか、……と。
「7階です」
と、スピーカーから音が鳴る。
「着いたな」
「ええ」
俺たち含め、乗っていた乗客の半分ほどが7階で降りる。同じ目的地の人が多いのか。それだけ、老舗の名前は伊達では無いということだ。
――詠鳥庵、恐るべし、だな、これは。
「いらっしゃいませー。呉服、陶器のB級市、開催中でーす」
店員さんの声が元気よく響いている。催事場はだだっ広くて、何組かのセールが同時に開かれていた。
既に販売期としてはやや遅いとはいえ、未だ需要十分の冬物市とか、湯たんぽ、あるいはその他アイデア製品的省エネ暖房グッズ取り扱いの企画とか。この辺り、詠鳥庵の出店とあわせ、個人的に大いに興味がある分野だったりもする。
「……これが、B級ですか?」
詠鳥庵の展示スペースに入ると、セイバーが訝しげな声を上げる。入り口付近には呉服反物の類が飾ってあるのだが、確かにパッと見、そんな瑕疵など分かろう筈がないものばかりだ。艶やかな職人技が光っている、としか言いようがない。
「な、わかんないだろ?」
「そ、そうですね……。私なら、これほどのものを縫い上げてくれば、間違いなく褒賞を出すところです」
そういう感想は、元王様っぽい。ともあれ、俺の感想も同じ。ただ、正規品として玄人さん筋に出すには、些細なミスであれ、その瑕疵はあまりにも大きい。だからこそ、こうしてB級と銘打って素人さん筋に打って出るわけである。
「だよな」
「ええ。……まあ、私は王でしたので、このような女物には縁が無かったでしょうが」
「でも、今なら似合うだろうなー」
「……!?」
「――あ、」
……言葉は、一度口から出たら帰ってこないのである。素直な感慨を口にしたつもりだが、あまりにも素直すぎた……と、言った後に気がついた。
「…………」
「……あー、あっち、だな。うん。器、見に行こうか」
互いに赤面、黙っていれば沈黙は目に見えていた。……うん、まあ、別に嘘をついたわけでもないので、いいのだけど……。
とにかく、黙り込んでも仕方ないので、それだけ提案してみる。
セイバーもその表情に苦笑を浮かべ、頷いて肯定の意を示してくれた。
――と。
「「――あれ?」」
「おや?」
後者がセイバー、前者が俺と、俺たちを見たその人の反応である。
その女、黒豹の如し――と、穂群原にその名を轟かせる女が、声の主であった。

「あれあれあれ、衛宮じゃん? と、そこにいらっしゃるはセイバーさん」
「こんにちは、楓」
「よ。家の手伝いか?」
「そーなのよー。今日はWiiでスペクタクル大河恋愛アクションゲームが発売だってのにさー、いきなり親父に捕まってタダ働き、ってわけー」
蒔寺楓。穂群原陸上部でエースを張った女傑であり、今なお、その影響力は校内に大きく残っている。冬木の老舗呉服商、詠鳥庵の一人娘、という地位まで持っていたりするその少女は、秋らしい艶やかな色彩、紅葉をあしらった和装に身を包み、そしてその服装に全く似つかわしくない口調でこちらに話しかけていた。
「やー、丁度手が開いた所でね。グッドタイミングだな」
「ふむ、和装なのですね、楓」
「お、これ? ま、家の方針、ってとこですね。従業員がフツーに洋服じゃ、雰囲気も出ないですから」
……なるほど、そういうものかもしれない。
ともあれ、まずは本題。知り合いが居れば、聞きやすいのは当然のこと。
「今日は、茶碗探しに来たんだけどな」
「お、そりゃ丁度いい。新進気鋭の冬木郊外窯、冬木焼特製のB級品が揃ってるからな!」
「……特製の?」
「そ。真の民芸運動を目指す、っていうコンセプトでウチと組んでやってる窯なんだけどね。やっぱさー、ウィリアム・モリスとか柳宗悦とか河井寛次郎とかの思想は立派だけど、結局大衆からは離れちゃったと思うわけよー。高いだろ? ああいうの。だから、本来の趣旨を活かしたブランドをだな……」
……そういえば、こいつは歴史だけ超・詳しいことで有名だった。所謂「民芸運動」についてアツく語る蒔寺の姿は、歴史ヲタクの片鱗を感じさせる。
「……ま、そんなわけでさ。A級でもそんなに高くなく、かつ、ちょっと失敗したデザインのとか焼きミスとか、大衆受けとかのをB級で市販してるわけ」
「民芸運動……か」
確かに、その名前だけで判断すれば異様に高い陶磁器なんかを思い浮かべてしまう。ここでいう「民芸」とは、物産店に売ってる土産物なんかを指すのではない。蒔寺が語ったような作者の手になる著名な皿やら壺やらに行けば、それこそ万金が動くものばかりなのが実情だ。
つまり、そうなってしまった運動の帰結に異を唱えている、ということであり、詠鳥庵がその先頭に立って真の民芸を打ち立てよう、という蒼穹の志を発露させた、のか。それも結構なことだし、こだわりの手作り品を廉価で提供してもらえるのは、消費者として大変にありがたいことであることは間違いない。
「だから、B級ってもそこいらの市販よりはこだわってるはず……と」
「お嬢様、ここの皿、陳列切れました。在庫から補充しに行ってくださーい」
「……これから休憩のはずなんだけどなー。ま、しゃーないか。じゃ、ごゆっくりー。茶碗はあっちのほうにあるからさ」
「ん。ありがとう」
「では、また後ほど、楓」
ひらひらと手を振ると、蒔寺は腕まくりして呼ばれた声のほうに向かっていく。
……優雅なのかなんなのか、よく分からない絵面であった。
「……どう?」
「似合っていると思いますよ。ああいう姿は想像していませんでしたが、中々」
「イメージとはかけ離れてるのにな」
似合ってる、というのはこちらも賛成である。なるほど、世の中にはまだまだ分からない取り合わせがある、ということだろうか。
「あちらでしたね、お茶碗は」
「ん。見に行くか」
さて、蒔寺嬢御推薦の冬木焼。
後学のためにも、じっくり見学させて頂きますか。
「なるほど」
言うだけのことはある、というのが率直な感想だった。セイバーと別行動で食器を物色していたが、粋というか趣というか、何かを感じさせてくれる食器群。シックな感じなものを選んでいけば、統一感も出そうである。
「食器の買い替えはこれもあり、かな」
次の売り出しがいつか、蒔寺に確認しておかなくてはならない。割れたりするまでは買い替えないものだが、あるいは新しい用途の器があってもいい。料理は盛り付けもその範囲内に含むもので――
と。
「お」
ふ、と移した視線の先に、ひとつの茶碗を見つける。吸い込まれるように見入ったのは、その意匠が気に入ったからに他ならない。
藍色の絵付けで、さりげなく一輪の花があしらってある。派手さは無いが、落ち着いた佇まいが、ワゴンの中でも一際存在感を放っている……ように、見えた。
色合いもそうだが、その在り方は、どこか彼女を思わせるような。
「……これに、するか」
そこに惹かれた、のかもしれない。幸い、サイズもちょうど良いし、と、茶碗をワゴンから手に取り、裏の値札を見る。日本円にして二千円。多少高いが、長持ちさせればいいだろう。ここは蒔寺の御推薦に従っておくとしよう。
「あっちはどうかな?」
ちょっと離れた場所、大きめの茶碗やどんぶりを並べてあるワゴンの前に居る彼女に目を向ける。さて、セイバーはお気に入りのものを見つけられただろうか?
「セイバー」
「あ、シロウ」
決めた茶碗を携え、セイバーに声をかける。丁度選び終わっていたのか、セイバーもまた、茶碗を手に持っていた……
「……って」
「二千円は予算内でしょうか? もしよろしければ、こちらにしようかと」
そう言ってセイバーが差し出したお椀のサイズは、大きめのもの。これで一膳食べればがっつり行けるだろう、というものである。割ってしまったものと比べても、遜色ないサイズ。
が、問題はそこではなく。
「……?」
そこで、ようやくセイバーも気がついたらしい。俺が手にしている茶碗を見つめて、自分のものと見比べている。
それも、当然の反応。
セイバーと俺が選んだ茶碗は――偶然にも、同じ柄の、サイズ違いだったのである。
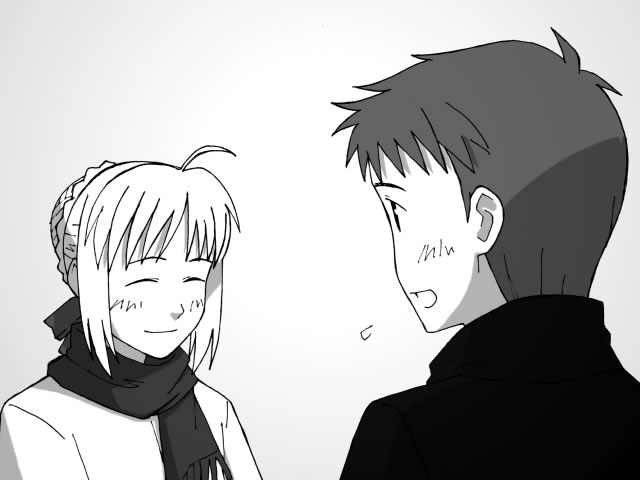
「――――」
「…………」
互いに、手に持った陶器を見て、顔を合わせる。……偶然と言えば偶然だが、これはまた。
「……ははっ」
「……ふふっ」
珍しい、と言えばこれほど珍しいこともない。
これも、何かの縁――と、いうことだろう。
「じゃ、これにしようか」
「はい」
使い勝手は、使ってみなくては分からない。
ただ――なにか、どこか嬉しい、そんな気分。
お気に入りの柄、丁度いいサイズ。ただ、それだけではない――本当のお気に入りになりそうな気が、どこかでしていた。
「毎度ー……って、お」
「店番?」
「ご苦労様です、楓」
レジに茶碗を持っていくと、先程手伝いに狩り出されていた黒豹が、今度はレジ係をつとめていた。和装のレジスター、というその様子は、妙にこの企画展にマッチングしていて面白い。
「お買い上げどうもー。税込みだから、2つで四千円ね」
「ん、じゃあコレで」
「はい、五千円お預かり。お釣りはこちらです」
レシートと共に、千円札を一枚を手渡される。
「ん。この陶器市、たまにやってるのか?」
「そうだなー。冬木焼の投入は今回からだけど、また次もあると思う。結構売り上げあるしな」
「そっか。じゃ、また来るよ」
「お、毎度。宣伝ヨロシク!」
「了解。じゃな」
「それでは、楓。また会いましょう」
「うっす。じゃ、また!」
蒔寺に手を振り、陶器市を後にする。すぐ後にまた別のお客さんがレジに来ているから、蒔寺の言うとおり、人気の企画展であることは間違いなさそうだ。
「楽しかったですね」
「たまには焼き物もな。また来よう」
「ええ、是非」
次の約束を軽やかに交わし、腕時計に目をやれば、丁度正午頃、と言った具合。
「じゃ、飯でも行こうか」
「いいですね。時間も頃合ですし」
セイバーの腹時計は正確無比。昼飯を前に勇むセイバーを微笑ましく思いながら、俺とセイバーはレストラン街へのエスカレーターへと向かっていった。
「……って、……んー」
……衛宮士郎とセイバーが詠鳥庵主宰の陶器市を去って後、数分。その後に来たお客数人を捌いた楓は、一人腕を組んで思索していた。
「……あれ、……なんだろ?」
気になるのは、さっきの二人組に他ならない。なんか違和感、なんというのか、あの二人は、なんだろう、フツーの一般に言う「二人」とはどうも違うな、とかなんとか。
「んー……あ、いらっしゃいませー」
しかめ面で考え込み、更に何分か。お客への対応もこなしつつ、楓は考える。
「ていうか、あれって……」
あれだよな、アレ。と、楓は心中で繰り返す。その該当する単語が出てこないで難しい顔をしていた楓は、その後約一分で、漸く目当ての言葉を思いついた。
「ああ、そっか」
ぽん、と手をたたき、楓は頭上に電球でもついたかのような表情をする。
「付き合ってんのか、あの二人。道理で、あの茶碗――」
あまりの自然さに、楓はその事実をストレートに直視できなかったのだろう。思考がここまで到るのに要した時間は、十分弱。が、ようやく事態に気付いた楓は、我が意を得たり、という表情を浮かべ、スッキリとした気分で仕事に戻る。
また学校でのネタが増えた――と、心中でこっそりニヤケながら。
すすむ
もどる