〜Interlude in 2-1〜
掌にかかっていた重みが消える。背後の気配を感じながら、朝日の近い山並みを、視線の先から明るくなっていく空を見つめていた。
戦いは終わった。彼の剣となり、彼の意思を貫き、彼の敵を討った。彼の隣にあれてよかった。
――――――長く、長く息を吐いた。
今は切り伏せる敵もなく、向けられる敵意もない。どこまでも透き通った心持ちで朝日を見つめている。互いに言葉はなかった。ただ、誓いだけが其処にあって。
彼の言葉次第、それで、この身の在り方は決まる。少しだけ唇を弛めた。だって解っている。二人で階段を上ったあの時から、私にかける言葉など、とうに尽き果てて居ることが。
おかしいと言われた、間違っているとも。それでも貫き通した意志を、彼は尊重してくれたのだ。だから、これでお終い。何もかもが揃っているのなら、これ以上は必要ない。ただ綺麗な姿のままで、綺麗な想い出のままで彼の中に在るのなら、それだけで十分すぎる報いといえるだろう。
もはやこの身を繋ぎ止める物はない、まるで布に鋏を入れるよう。ざくりとラインの断ち切られたのが解る。風にほつれていく。外側から順番に、ドレスが端から朝日に溶ける。もう終わりなのだ、悲しみはない、心残りもない。ただ、これで終わりだという感慨だけがある。存在が軽くなっていく、気を抜けば、それだけで消えてしまいそうな頼りなさ。ぐっと堪えて、彼へと振り返った。
「最後に、一つだけ伝えないと」
「ああ、なんて」
落ち着いた声だった、透明な顔だった、全ての終わりだと知って、それでも受け入れてくれている。私の我が儘を、私の祈りを、私が、残す言葉を全て。
だから残すのだ。
本当の心を、伝えなければならない言葉を、繰り返せば安くなる、たった一度の誓いを。
声に宿れ、万感の思いよ。
彼に届け、最後の誓いよ。
「シロウ――――――貴方を愛している」
朝日が私を貫いていく。最初の光に目を眩ませて、彼が瞬く間眼を瞑る。
それが最後。見ることの出来なくなった瞳に焼き付いた、最後の姿。
――――――そんな、幸せな娘の夢を見た。
――――――暖かい日差しに、細く瞼を持ち上げた。
それだけで意識が遠のく、微かに瞼を持ち上げることすら、今の私には重労働。単純に血が足りていないのだろう。かすむ視界に写る緑に、何とか焦点を合わせるよう試みる。どだい無理な話だった、最早我が目は目として機能していない。ただの碧玉。碧の宝石と同じだった。
おとぎ話のようだと思った。力を失った瞳は宝石に変わる。古い伝承を信じるわけではないが、似たような物だと思う。
ああ、本当に宝石に変わるのならば、誰かの糧にはなるかも知れない。朽ちていずれ土に帰るのならば、せめて何かの役に立てばいいと思った。
音が聞こえる、馬蹄のとどろきは軽く、それが一騎だけであることを知らせていた。次いで、騎士の足音。首をうなだれたまま戻ってくるのだろう、いつものような切れはなく、ただ忸怩と重い。
見えているわけではないが、どのような表情をしているのかはっきりと解った。我が身の傍らに、長く置いた騎士。彼を計るために、彼を見つめ続けた。
それが、何の役に立ったかと問われれば、首をかしげざるを得ないが。
この最期の時に、いかな表情をしているかぐらいは、見ずとも解った。
「誇るが良い、そなたは――――――王の命を果たしたのだ」
耳は耳として機能していない。枯れた声は遠く、己の物ではないようにも思える。何とか瞼をこじ開ければ、光を失いかけた瞳に辺りの風景が映り込む。疲れ切った頭は、それすらも理解を拒んでいて。
穏やかな場所だと、それだけが理解できて。まるで己が横たわる場所には似付かわしくない。在るべきは戦場で。前線は遠く、帰るべき城も最早無い。敵は消え、騎士も散り、理想も露と消えた。
――――――ブリテンは滅びた。
剣は折れずとも、私の戦は此処までだった。
寒かった。出血は止まないのか、未だに頬を流れ落ちる物がある。むずがゆく、鬱陶しい。震えはしなかった。それだけの体力も最早残されていないのか、ただ泥のように木の根にもたれ掛かっている。横たわればそれだけで命を落としそうで。
泣き崩れそうな騎士に、目をやった。
私は言った。
夢を見ていた、と。
ベティヴィエールは答えた。
強く願えば続きを見られることもある、と。
その博識さに、閉じかかる目を見張った。暖かい物が、胸に込み上げてくる。
ならば願おう。この後眠りに落ちたときに――――――あの夢の続きを、と。
「済まない、今度の眠りは、少し、永く――――――」
息をするのが億劫になってきた。
死ぬのは良い。
死ぬのは良いが、夢の続きを見られなくなるのが心残りで。
叶うのならば、安らかな眠りを、と。
忠実な騎士に見守られながら、願わずにはいられなかった。
――――――幸せな娘の夢。
戦いも在れば、剣も傍らに。
それでも――――安らぎに満ちた腕に抱かれた――――――
「微睡みの終わり」
Presented by dora 2007 02 17
改稿 2007 11 20
――――――白い闇に包まれている。
抱き上げられ、布にくるまれたのを感じた。たおやかな腕と、皺くれて、だが力強い腕とが我が身を支える。叩き付けるような音、強い雨が降っているのか。ただ、それも我が身に及ぶことはない。如何なる力も、呪いをかき消すことが出来ないのか。モードレッドの剣による傷は、癒えることも腐ることもない。ただ、終わりに続く痛みだけを残している。
割られた頭蓋がまだ痛むのだ。担ぎ上げられ、運ばれていく。何処へ行くのか。それすらも気にならぬと言うのに。高い景色は馬の背のよう、揺れる体の上で考えた。
まだ生きているのか。
魂魄が抜け出していないだけで、私は死んでいるのか。
どちらともつかないままに、船に乗せられる自分を見ていた。いつのまに抜け出したのか、気が付けば我が身を空から見下ろしている、高いところからの視界は、思ったほど心を動かさなかった。荒れた海と空、ねずみ色の浜辺。まるで海鳥に変わった様。寂しい風景はそれだけで涙を誘う。雑音は耳を塞ぎ、その全てに憶えがあって。
大きな船ではなかった、外洋をわたれるほど、強くない。
むしろ、小舟の類だった。十人も乗れば、ひしめき合って息苦しくなるような類のそれ。
何処へ――――――行くのだろうか。
其処には姉が居た。他にも見知った顔が幾つも。尋ねようにも声が出ない。ふらふらと動き回ってみたところで、海図の一つも見あたらない。結局何処に行くのかは解らなかった。
風は冷たかった。青かった草原も遠く、白亜の城もここから見えはしない。砂浜から船がはしりだす。揺れる波が、船体に当たっては砕けていく。静かに響く音が何とももの悲しい。
溜息を吐いた。横たわる己の骸の隣で、長く細く息を吐く。望んだのは、こんな夢ではなかったのに。
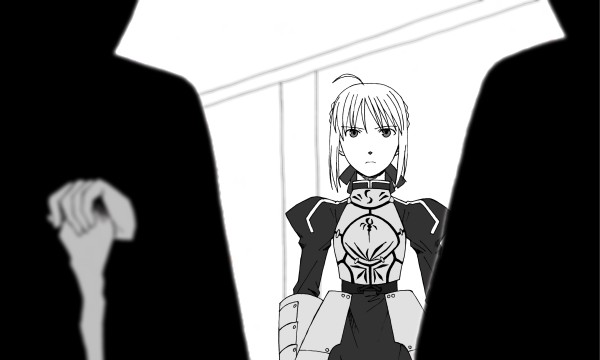
己が身をかき抱いて、寒さに身を震わせた。霧に包まれた海は底冷えする、毛皮の一枚でも欲しいところだった。出来うるのなら暖かい――――――
『え、と――――――』
――――――その暖かい声。
揺れる湯気の向こうの彼。
火花が走るように、それを思い出す。
同じ水なのに全く違う、霧とは違う湯気の向こう。安らぎと温もりに溢れた湯殿と、その向こうに見え隠れする、赤い髪の少年。
心臓が大きく跳ねた。止まっては居ないのか、それとも心臓ではないのか。とにかく胸が痛かった。
『とにかく、すぐに出るから、いや、でもその前に謝らないとマズイ』
『――――――』
言っていることから意味は読み取れず、ただ困惑しながら彼を見ていた。
『私の腕は、筋肉がついているからみっともない』
あの時は、そんなことを言ったのでは無かった筈なのに。
口が勝手に動いていた。見られても何ともなかったのに、今は見られたくなかった。
恥ずかしい、と。
初めて思った時だった。顔が上手く見られなくて。
「――――――」
手を伸ばして我に返る。
嫌な幻覚、此処は湯殿などではなく、冷たい霧の中で。
彼など、何処にも居りはしないというのに。
「む――――――」
ふと、それに気がついた。
波の荒さが、ふるさとの物ではない。空気の匂いも違う。見上げた夜空には、星が見えていた。妖精境にでも、連れて行かれるのだろうか。
私は、林檎の木の下でなど、眠りたくないのに。
眠る、僅かな間、何かを願ったのではなかったか。思い出せそうで思い出せない。夢は続けざまに見られる物だと、忠実な騎士が言っていた。それも悪くはないか、そう思い直した。
夢を見られるかも知れない。戦場から見続けた、せめぎ合いのゆめ。
それは望むべくもない夢だった。此処とは違う何処か、今とは違う何時かで、剣を振るう夢。傷ついて血まみれではあったが、幸せな夢を見ていたと思う。
暖かく、愛情に満ちた夢。全てが其処にあり、今の自分を誇って良いと思った。乱暴に扱われたこともある、だが、夢の中の彼は私を女として終始扱った。
深く、幾度も首をかしげた。
喉の奥に魚の小骨が掛かるように、がけの上まで今一歩手が届かないように、後一撃のところが決まらないように。
もう一度空を見上げた。まるで日暮れ時のよう、見えているはずの星がほとんど見あたらない。満天の星空と言うには程遠く、ちらちらと弱々しく瞬く星が冷たい。
彼のために、星を読もうと思った朝すら思い出せるのに。
唇を噛んでこめかみを揉む。だが届かない。記憶のそれが――――――壊れている。
どうしても名前が思い出せない。思い出せそうで思い出せない。まるで、目で見たそれが文字に書き換えられていくように記憶から抜け落ちていく。記録された本を抱きしめた。声も、音も、何も残されては居ない。だと言うのに、ただ激情だけが荒れ狂って。
いつしか、抜け出た私は体に戻っていた。目を開くことも出来ないままに、もどかしくて腕を伸ばした。
それを、優しく握り返した手。
震えが走った。
憶えがある。
記憶にも体にも、その力も温もりも刻み込まれている。力の限り握りしめた。
これは兄様の腕か。
否、違う。と、僅かな時間で否定した。
兄様の手は、此処まで大きな手ではない。今の私では知らない手だった。何時かの遠い日の私が、一番欲したのはそれだった。今でも――――――
閉じた瞼の隙間から、後から後から涙が流れる。頬を伝うそれすら懐かしくて。
優しい手だった。ごつごつとして、ささくれて。
愛した夢の彼の手。血を吐く思いだった。だってそれでも名前が思い出せない。
止めろ。
開かない口で叫んだ。止めろ。この船を止めろ。
理想郷へと向かう船を、止めろと叫んだ。
其処は私が行きたい場所ではない。私が行きたいのはそんな場所ではないと。
眠りに落ちてまで欲した、優しい夢の続きをどうして見せてくれないのだと。
それは子供のかんしゃくにも似て。
生きたまま埋葬されるのと何が違う。
握られた手だけが温もりの頼りで、ただそれを握りしめた。
〜Interlude out〜
日差しの下で微笑むセイバーと。
どこか遠い土地へ、旅をしている夢。
優しい、暖かなそれは――――――
「――――――夢か」
付き添いに座るソファの上で、聞こえた呻きに目を覚ました。どうやらまるで気が付かぬ間に居眠りを決め込んでいた様子。一息には覚醒しない頭を振って、意識を取り戻す。何気なく時計に目をやって驚いた、時刻は一時を回っている。
溜息が漏れた、緩むにも程がある。不寝番を買って出たのに眠っていては話にならない。まったく、いつの間に眠っていたのか、不覚を恥じながらセイバーの元へと思い席を立った。苦しげにうめく額に手を乗せる。寝起きの冷えた手に、額が熱い。
心配と同時に、安心もする。良い兆候だった、熱が出るのは、体が回復に向けて動いている証だ。活発に体が回復を望んでいるのか、それなりに温度は高い。脇の下に押し込んだ電子体温計が、38.2度を表示する。
「結構高いな」
タライに指を浸してみる、幸い、汲み置いた水はまだ冷たい。今の季節なら、隣の部屋なり廊下なりに置いておくだけで、冬の大気が充分熱を奪ってくれるだろう。タライから手拭いを取り上げると、固く絞って額に乗せた。
ふ、と意識に滑り込む甘さ。先程までの鐵臭さとは違う。肌の匂いも、汗の臭いも、彼女が生きていることを教えてくれる。
「セイバー」
呼びかけに答える音はない、ただ、喘いでいる。冷えた空気を求める荒い息だけが響いて。
不意に彼女の左腕が跳ね上がった、何かを求めるかの様に、中空を手が彷徨う。剣を求めているのか、と思った。枕元のそれをか、とも。大きな間違いだった。手の届かないところに手を伸ばすようなそれは、誰かを追いかけるようにも見えて。
そっと手に手を寄せる。握った瞬間に握り替えされた。思いの外強く、それを手だと知って握ったのだと一瞬で理解する。ぎゅっと握られた強さは、何時かの夜、絡めて寝た指の強さと同じで。込み上げる物に、息が詰まってしまいそう。
それは強くて優しい手だけの抱擁。力一杯握り替えしてくるくせに、そのくせおずおずと指先にためらいが残っている。出来ることならそのまま抱きしめたかった。いっそのこと、このまま殺してくれとも。未だ何も成していないけれど、この場で終わりにされるのならば、それも良いと思った。
何てな。せっかく逢えたのにさよならなんて、切なすぎて死にきれない。
ぐっと、胸元に手が引き寄せられた。手放すことを恐れるように腕がかき抱かれる。寝間着の下は素肌なのか、控えめではあるが、確かな女の感触にどぎまぎする。赤くなる顔をそのままに、ただ視線を下げた。
生きている。
手から伝わる温もりが、押しつけられる胸の柔らかさがそれを伝えてくれる。
生きている。
彼女が其処に居るだけで、ただ嬉しかった。
拘束が徐々に緩む、悪い夢は去ったのか。浮かんだ汗をぬぐおうとして、頬を伝う涙に気がついた。
「セイバー」
何故――――――お前が泣いているのか。
うわごとに耳を傾ける、おぼろげなようで何処か具体的なそれは、耳になじんだ言語のままで。言葉の一つ一つが胸に突き刺さる。悲しみと、嬉しさと。何よりも愛情が溢れていて。
日本語、それも、聞き覚えのある音で。確かに、今彼女はこの時に生きた事を思い出している。込み上げる物が胸に詰まった。呼吸を忘れて、涙を溢れさせる。
其処ではない、と。
私は林檎の木の下で眠りになどつきたくはないと。
私が望むのは――――――かの人の傍らで夢を見ることだと。
いくら揺すったところでセイバーは目を開かなかった。昏睡は深く、そのくせ夢を見るぐらいには浅い。熱のせいで胡乱過ぎて、目を開いたところでそれもまた夢なのか。
言葉の一つ一つが胸を抉る。こんなに近くにいるのに、こんなにも遠い。ぼろぼろと涙がこぼれてくる。どうしたって届かない距離、目の前にいるのに触れられない眠り姫。
どうして、どうして名前が思い出せない。
そう、知らない自分を呼び続けるセイバーが愛おしくて悲しかった。
あくまでも自分は夢の中の登場人物。
明けて醒めれば忘れかねない思い人。
だが――――――それでも良いと思った。とうの昔に逢えないことを理解していたのに出会えただけで満足。
この先、一緒に歩いていけると夢想しただけで、胸が溢れて仕方がない。
「セイバー、大丈夫だ。何があっても俺は傍にいるから」
声にならない音を押し出して、やっとの事でそれだけを告げる。其処に意味なんて無く、ただ己の言葉のみがむなしく流れていく。
それでも、それは言っておかなければならないことだった。
取るに足らない言葉だが、永遠の誓い。全てを賭けてお前を守ると、願わずには居られなかった。
あの時に聞いた誓い、永遠の別れになっても構わないと。ただ思いさえ其処に残ったのなら満足だと。忘れるはずがなかった。
ぬるくなったタオルを洗い、堅く水を絞る。それを額に乗せたときに、微かにセイバーが目を開いた。定まらない視線が、部屋の中を彷徨っている。ふらふらと漂う視線が、一度だけ己を捉えた。
「――――――?」
確かに、確かに名前を呼ぼうとした。
だけど思い出せない。そんな苛立ちが再び目を閉じさせる。
だが捕まった。手が彼女に捕まった。
何より、一年ぶりに見たあの瞳が――――――心を捕らえて離さない。僅かに綻んだ唇は、安堵のそれなのか。
乱れがちだった呼吸が、徐々に穏やかなそれに変わる。ほっと息をついて、ベッドの端に伏した。昼間の疲れも相まって、少し目を閉じるだけで微睡みが
願わくば目覚めが彼女よりも早いことを。
彼女におはよう御座いますと言われる前に、俺が先に言うんだと。
そんな、小さな願いを夢に描いていた。
鳥の鳴く声に眼を覚ます、不自然な体勢で眠っていたためか、どうにも体が軋んで仕方がない。
なにはともあれ、彼女の容態を確認する。眼を覚ます気配はない、深く長い呼吸は、寝息そのもので。熱は下がっているのか、苦しげに弾んでいた息も今は規則正しく、緩やかにシーツが上下している。ただ、顔色は良くなかった。治療を開始したときの出血は激しく、夕べの発熱で体力の消耗も激しかっただろう。目は落ちくぼんで、頬にも影が見えている。缶のスポーツドリンクを水差しに移すと、彼女の唇にそっと触れさせた。弱々しくだが、流れ込むそれを喉が嚥下していく。目をやれば白くて細い其処にも、無数のひっかき傷があって。
そっと額に手を載せた。先に思ったよりも、熱が引ききっていないのだろうか、ほのかに掌よりも熱い。無理もないと思った、傷はもの凄く深かったと、遠坂から聞いている。このまま昏睡が続けば、衰弱していくだろうとも。
ぱたぱたと聞こえてきたスリッパの音に、顔を上げた。暗くなっているだけの余裕など無いと、足音が急かすように。丁度ベッドを挟んで反対側、控えめなノックと共に、扉が開く。
「おはよう遠坂」
「おはよう衛宮くん」
外はまだ暗い、だが、一度眠った彼女が起きてくると言うことは、それなりの時間だと言うことなのだろう。視線に促されて時計に目をやると、午前六時には僅かに足らないぐらい。夜明けまで、あと少しと言った具合だった。
「そろそろ一度帰った方が良いんじゃないの?」
「けど――――――」
「私と違って卒業までの生活態度が響くんだから、まじめな所を藤村先生に見せて置いても損はないと思うわよ」
提案はもっともで、異見を差し挟む余地など無い。彼女のことは大切だが、任せてくれと、遠坂が言ってくれている。最高に信頼の置ける相手だった。
「…………うん、まあそうだな」
「後は見ておくから」
「わかった、世話になる」
「ちょ、やめてよ!」
立ち上がって頭を下げた。ありがたくって申し訳なくって、他に言葉なんて出なくて、言える事なんて、それぐらいしかなくて。
ばしん、と、部屋に破裂音じみた張り手の音が響く。それを音と認識する以前に俺悶絶。ていうか、何をトチ狂った遠坂。いきなり人のシャツまくり上げてモミジはなしだろうっ!?
「――――――っはっ、あ、……ぃぃいっ!?」
声が出ねえ。
ってか言葉がねえ。
このバカ、いったい何しやがる――――――!
痛みにもだえながらも、必死に背筋を伸ばす。歯を食いしばって睨み付けながら、一旦は離れた距離をぎくしゃくと歩み寄る。そんな怒りなど何処吹く風と、俺の背中と同じくらいに紅くなった右手を振りながら、遠坂はまるで悪びれずにこちらに指を突き付けた。うっかりガンド、大真面目に考えて横に逃げる、それが気にくわなかったのか、更に一歩詰め寄って彼女は言った。
「水くさい事いわないでくれる? 言っておくけど、これは私の友人に対する礼儀であって、衛宮くん
が頭を下げる事じゃないわ」
「それとモミジは関係ないだろ、なにしやがんだ!」
「あら、これでいいんじゃない? 私は頭下げないから、アンタも頭下げる理由が無くなったわね」
「この…………素直に頭上げてくれとか言えないのかよ!」
「誰が言うもんですか!」
にらみ合い、この、感謝ぐらい素直に受け取れってのに。意地っ張りなのはお互い様、このままこうしているのも不毛なことこの上ない。大きく息を吸って、意地を引き込めることにした。
「わかった、悪かった、世話になるから後頼む」
「OK、任せて。ホラ、早く行かないと時間無いわよ」
本当に良い笑顔をする奴だと、短い間友人の顔を見つめていた。
早朝の空気の中、緩やかに明けていく夜を惜しみながら坂道を走り出す。場合によっては桜を追い越すかも知れないが、それは早朝マラソンと言って誤魔化してしまおう。そんなことを考えてもいたのだったが、幸い見知った顔に出会すこともなく、屋敷に到着した。
「ただいま」
がらがらと戸を開けて玄関に上がり込む。遠坂の屋敷から衛宮の屋敷まで、大した距離とも言えないが、走っただけあって、うっすらと汗が滲んでいた。考えてみれば、朝起きてから顔も洗っていないのだ、べたつくのが嫌で、風呂にはいることにした。さっぱりした頃には、誰かしら家に上がってくるだろう。
そんな事を考えながら、ざっと熱めのシャワーを被る。髪の毛の間から、疲労が形になって流れていくよう。くぁー、なんて声を上げながら顔を洗う。思ったよりも疲労が抜けていないのか、何だか今にも眠ってしまいそうな頭の蕩け具合。
短く切り上げて、部屋に向かう。学生服に袖を通すと、何だか朝食の支度をするのが面倒になって寝ころんだ。今日は桜に任せてしまおうか。
「…………あ、ヤバ」
つらつらと眠りに誘われている。まあ、まだ時間も早いことだし、朝寝しても誰かが起こしてくれるだろう――――――
「――――――ぱい、センパイ」
「ん、うん、起きる」
桜の声に眼を覚ました、家の中を捜していたのか、思い起こせばちらほらと聞こえていた気がする。大きく伸びを一つ打って、固まりかけた頸を二三回ならした。
「おはよう御座います。センパイ、起きてますか?」
「おはよう、今行くから」
わしわしと頭を掻いて、立ち上がった。すっかり制服に皺が寄っている。このまま寝ころんでいたのは失敗だったかと考えながら、居間にむかう。
腹は減っていた。いつもより運動量が多かったと言っても良い一晩。八時頃から何も食べていない事を考えれば、この強烈な感覚も納得がいくという物で。
「お、今朝は――――――ほっけか」
「あはは、昨日安くて良いのがあったんですよ」
「に――――――してもこれは」
ででん。とでっかく皿に自己主張するほっけ塩焼き、さあどっからでも食ってくんなと勇ましい。どちらかと言えば晩飯に並ぶようなサイズが人数分。これはイリヤなんかじゃ食べきれない気もするのだが。
「間桐軍曹」
「……大きい、ですよね?」
「だよな。まあ、いいけど」
……余ったのならふりかけにでも作り替えてしまえばいいだろう。ぱっと浮かべたレシピには煎り胡麻と海苔。細かくしたほっけをそれらと合わせるだけで、ご飯が三杯は行けるのが出来るだろう。
「おっはようなのだ〜!」
「おう、おはよう」
「シロウ、おはよ」
「おはよう」
どたばたと上がってくる足音に、挨拶を返した。イリヤは少し眠りが足らなさそうで。さっそく箸を持って「いただきます」なんて動き出す虎を尻目に、そっとこっちに寄ってくると耳元に手を寄せた。
「ね、シロウ」
「んん?」
怪訝に思い耳をそばだたせる。こら、そこの虎と義妹、聞き耳を立てないように。
「どうした?」
にっこりと微笑む彼女、イリヤはそのまま唇を耳に寄せると――――――
〜To be continued.〜
メールフォームです。
dora様への御感想はこちらからどうぞ!!→メールフォーム
dora様の寄稿なさっておられるHPはこちら!

戻る
玄関へ戻る