〜Interlude in 2-10〜
「じゃあ順番に見て回ろっか」
彼の言葉に静かに頷きながら、目を閉じたままイリヤスフィールは言った。順番に、とはどういう意味なのか。見回る場所に手順でもあるというのか。何処を遊覧するのだろう。己が連れ回される場所は判らない、だが、不安はなかった。
「ああ、よろしく」
彼女の言葉に、シロウがやはり静かに頷いた。
踏みしめる脚を噛み締めるように、三人で森の中を歩いていく。皮で出来た小さな靴は森の行軍に向いていなかった。滑る足下を支えようと、知らず知らずに手に力が籠もる。それを優しく握り返す手に、僅かに体重を委ねた。
胸に吸い込んだ空気は湿って枯れたそれで。生い茂る森は鬱蒼として深く、何処か故郷のそれを思わせる暗さで。
ただ、あの土地よりも木々の葉が広い。冬枯れのそれも、落ちているそれも。冬の空気が更に冷やされたそれを吸い込みながら思った。木々の気配が濃い。古い木が多い証拠だった。
小一時間も歩いただろうか、茂る雑木の切れ間から、遠くに森の切れ目が見えてきた。なんだか、久しぶりに空を見た気がする。鳥の声もなく、動物の気配すらないアインツベルンの森は、遙か西欧の本拠地と同じく、確かに結界で包まれている。陰鬱な、重苦しい魔術師の本拠。閉じこめられた空気は甘く停滞して、服にも髪にもまとわりついて仕方がない。確かに此処も歪んだ土地だった。
―――遠い剣戟の残響が聞こえる。一撃と呼ぶには余りに巨大な暴力、弾き返すだけで精一杯の嵐。瞬き一つで確実に微塵にされる。そんな、恐怖の具現。あり得るはずのない神話の再現も、その歪みに拍車を掛けているのか。喩え目撃者が無くても、その有様は世界に記録される。積み重なった歪みは魔力に姿を変え、その土地に神秘を根付かせていくのだろう。あの激しい剣戟は――――――
吹き荒れる砂嵐に浮かぶ蜃気楼、憶えのない影だが、確かにこの身に刻まれたそれ。
また視界にノイズがかかり始める。足下がおぼつかなくなるが、かといって、記憶に己を飛ばすことがやめられない。頼りになるのはこの―――つないだ掌だけで。
そうだ。私は思い出したい。それを畏れているが、私は思い出したい。何か、何かあったはずなのだ。彼を信じたことがあって、彼を頼ったことがあって、信用から信頼へ、そこから、更に育っていった物が在った筈。見えなくなった目に、鉛色の巨体が迫る。一撃の重さが体を震わせる。鮮やかな宝石の輝きと、同じく鮮やかだった■、黄金の、失われた■の名は――――――
「セイバー、大丈夫か」
「はい、シロウ」
吹き流されるように、視界の砂が拭い去られる。歩きやすくなった地面を、確かに靴が噛んでいた。どれほど彼の手に体重を掛けていたのか、完全に狂っていた重心を元に戻す。
溜息を吐いた。完全に体重のよれた私の体は、頼ると言うよりも、寄りかかっていた。と、いった方が正しい。
情けないような、こそばゆいような。
何とも言えない心持ちになった。
「手、離そうか?」
「……いえ、いましばらくこのまま御願いします」
血の気が引くような。
頭に血が上るような。
熱くて寒い不気味な空気を顔に感じている。
気が付けばとうに森の外に出ていて、薄く曇った空が目に眩しい。
立ち眩みだろうか。冬の日差しにはそんな毒々しさなど無い。だというのに―――目が回って仕方がなかった。視界はクリアーになっても、溢れるそれは私を押し流しそうになっている。生まれ落ちてからの記憶すら凌駕する二度の戦争が、私を塗り替えてしまったのか。
殊に。
あの二週間が。
目の前にあるのに、掴めないその――――――
〜Interlude out〜
「微睡みの終わり」
Presented by dora 2007 03 04
改稿 2008 03 22
細かい枝が行く手を阻む。頬をひっかいていったそれを忌々しげな舌打ちとともに払いのける。跳ね返ってきた枝が、より強烈な一撃として額を襲った。葉っぱが落ちている分、ダイレクトにぺしりと鳴るそれは、割と鋭い痛みを肌に教えている。こう、思わず眼を瞑って額をさすりたくなるようなアレだ。
小さく呻きながら、セイバーに被害が及ばないように、空いた手で茂みをかき分ける。幾つもの小さなひっかき傷を作るのは、以前訪れたときと同じらしい。これじゃあイリヤも相当に歩きにくいだろうと目を向けると、鬱蒼と茂った森はまるで王の行進を妨げぬ民衆のように、左右に分かれていった。
ずるいぞ、イリヤ。
またぞろ厄介な枝が出てきた。そう思ってそれを押しのけると、唐突に視界が開けた。城の敷地とそれ以外を完全に割り切っているのか、森の境界線は枝を押しのけるまでそれと判らない。冬枯れの、丈の高い芝が足下で茶色く横たわっている。コレで最後だ。枝が跳ねないように気をつけながらセイバーの手を引いた。
ぐらり、と、預けられた体重に、よろめきそうになる。これでもかと踏ん張った。見ると、僅かに寄せられた眉の下にある瞳には力がない。何処か、遠くを見ているような虚ろさだけで。
「セイバー、大丈夫か」
「はい、シロウ」
返事にタイムラグはなかった。もう、一言二言何か声を掛けようとして、挙げられた瞳に絶句する、焦点があった瞳が、俺の視界を席巻する。見つめられるだけで、甘い毒が回るかのよう。
そう、血の気は一気に顔を蹂躙し、まっとうな視界を奪い去るその毒の名は――――――
「手、離そうか?」
震える息を押し出して、何とかそれだけを口に出した。
「……いえ、いましばらくこのまま御願いします」
一度踏ん張った脚から、また力が抜けていく。ただ、今度の脱力におかしさはない。安堵とともに抜けた力が、俺に委ねられていく。
浅かった呼吸も、徐々に整ってきた。一度緩やかに目を閉じると、今度こそしっかりとした足取りでセイバーが歩き出す。
幾度も自問してきた事、どうして此処まで彼女にこだわるのか。結局の所、惚れ直したと言うか、二度惚れしたと言うか。再会の悦びは、心の強さを取り除く。再び別れることなど、とうてい考えられなくなってしまって。
一度ぐるりと回り込み、正面から城門を潜る。スカートをふわりと広げながらイリヤが振り返った。
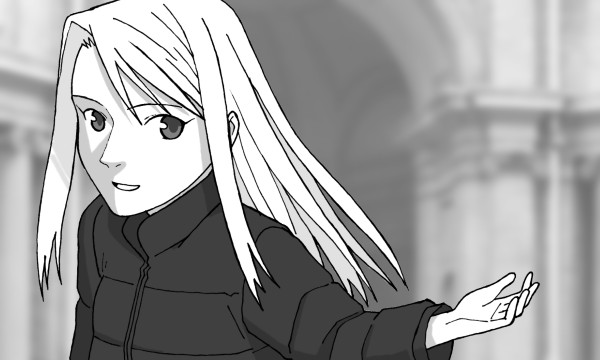
「ようこそ、我が城へ。イリヤスフィール・フォン・アインツベルンは貴方たちを歓迎します」
その様は実によく似合っていて、イリヤがいいとこのお嬢様なんだと言うことを再認識させる。対するこっちはしどろもどろ。生憎そんな礼儀に合わせる知識なんぞ持ち合わせては居ない。
「あ、うん。その、ご迷惑をおかけします」
ほらみろ、かっこわるい。こんなことやらせるなってのに。
「ん、堅苦しいのはコレで十分。シロウはいつものままでいいよ」
「うん、その方が助かる」
イリヤの許しを聞いて、こわばった肩の筋を伸ばした。これぐらいのことは出来なきゃいけないとは思うのだが、いかんせん日々を過ごすことに精一杯で、自分の時間を作り出す事がなかなか出来ない。
人のための時間だったら割と作れる辺り、衛宮士郎には本当に救いがない。
硬い靴音を聞きながら、長い廊下を、何時かとは逆に進んでいく。どこか、暗い印象を受けた。表現されているのは胎内回帰願望だろうか、グロテスクの語源になった様式とは違うが、どっか似たような洞窟式を思わせる装飾。
豪華ではあるものの、絢爛ではない。蝋燭の灯りが揺れているのに、廊下は怪しく暗かった。
この城は廃墟に近い。なんともなしにそんなことを考えた。不思議に思って首をかしげる。自分たちが帰るときにあれだけ荘厳だった場所だというのに、建物として機能していないような、そんな匂いがしている。
もう一度首をかしげた。些細な何かを隠すのに、がらりと印象を変えているような―――
長い廊下の果て。回廊の終わりにある一枚の扉を押し開いた。
「――――――うあ」
声をろくに出すことも出来ない。其処は、まるで戦争でもあったかのような有様で。部屋中余すところ無く、斬撃の荒れ狂った痕跡が留められている。壁も床も階段も、天井すらもずたずたに切り裂かれている。大きな一枚岩の天井すら、一撃の下に断ち割られたのか。大小様々な瓦礫がロビーを席巻していた。
身動きすることすら出来ず立ちすくんだ。
「どう? シロウ。これでも廊下は片付けた方なのよ」
「え、じゃあ」
あの様式は元からのものじゃなくて。
この破壊の有様を、修復してあそこまで持って行ったのか。
荘厳で荒涼とした風が吹く。遠い響きに耳を傾けるようにイリヤが言った。
「……誰だったのかしらね、あれは」
それは、あり得ない者を見た者の驚きか。呟きは硬く尖っていて、小さな彼女の胸を傷つけている。
「イリヤも判らないのか?」
「ええ、そうね。――――私は、識らない」
識らないわ、あんなデタラメなヤツ、どんな物語にだって出てこないじゃない。そういうと、イリヤは一つの瓦礫に腰掛けた。
「――――――」
最後に振り返った視界に写る紅い背中、右手に映し出された遠い剣。一年経った今でも鮮明に思い出せる。結局誰なのか判らない奴だった。何一つ自分のことは明かさない、信用のおけない奴で。だけども、それを補って余りあるぐらい、アイツは俺達を助けてくれた。アイツの振るった剣こそが、何よりの証だったと思う。
どれほどの間、そこで立ちつくしていたのだろうか。何を得たかは己のはかり知れるところではなく、最期の時に知る夢に過ぎない。そもそも今日の来訪はセイバーの為の物だった。疲れ始めているのか、そんな、意味のないことを考えながら踵を返した。
「――――――待ってください」
「え――――――?」
するりと手の中からセイバーが抜けていった。風に吹かれるように振り返る、と、彼女はある場所で立ち止まった。
「――――――」
喉が、張り付くように渇いていく。
アーチャーが居た位置。其処は、最後に彼を見た場所そのもので。
其処にセイバーが立って、振り上げた腕を、まるで見えない敵に振り下ろすかのように、さりとて急ぐこともなくゆっくりと動かしていた。
まるで夢を見ているような瞳の色。それを見るだけで、なんだか悔しかった。一言で焼き餅、つまらない感傷で胸を痛めている。
「セイバー、行こう」
「はい」
此処には何もない。ただ――――――剣戟の残響を胸に歩き出す。
いつか通った階段を、逆しまに上っていく。あの時は降りていくだけだったが、こうしてみてみると殺風景なようで徹底的に手の込んだ装飾が為されている。やはり長い廊下を歩いて、その部屋の前に辿り着いた。
「どうぞ、中に入っていいわ」
「ああ、お邪魔します……っと」
彼女に促されて、扉を開いた。途端に広がる温もりは、一日中しっかりと暖炉が焚かれている証拠で。広がる空気の柔らかさに、こわばっていた頬がほぐされていく。
――――むう、此方側から見るとこんな感じなのか、これでは何処に隠れようとも一目瞭然だ。俺が縛り付けられていたのは、あの辺りにあった椅子か。
部屋の中から見る限りでは、意外に死角になるんじゃないかと思っていたが、こうしてみると素通しも良いところ。察するに、セラが寝ているイリヤの様子を伺いやすいように設えられて居るのだろう。これはベッドに潜り込んだりしなくて正解だった。どう潜り込もうとも、丸見えでしかない。呆れられるか、最悪殺られていただろう。勿論味方に。激昂した…………やめよう。意味がない。
まあ、もっとも。
あの時は、誰であろうと一撃くれてでも脱出する気で居たのだったが。
「ふふ」
此方の渋い顔をみてイリヤが小さく笑う。あの時のことを思い出していると思ったのか、悪戯っぽく椅子の置いてあった辺りに視線を投げる。考えてみれば、結構危ないシチュエイション。うっかりあのタイミングで踏み込まれていたら、それはそれでBAD ENDだっただろう、主に俺の人生が。こう、倫理的に。
「あの時は結構怖かったな」
「どうして?」
「本気で人形にされるんじゃないかと思ったから」
「そうね、シロウが頷いてくれたらその場でお人形だったのに」
「……ホンキ?」
「もちろんじゃない、シロウは私のサーヴァントになる予定だったんだから!」
…………むう、マジで恐ろしいぜロリッ子。よかった、あの時口からでまかせその場鎬の嘘なんか吐かなくて。人形なんかに移し替えられた日には、彼女が迎えに来てくれても気が付かれることすらなかっただろう。
「あ、質問」
「許可します、なに? シロウ」
「その場合って、マスター権だとかってどうなってたんだ?」
「え? ん〜、と、そうね…………そう言うのってタマシイに帰属する物だから、マスター権はそのままなんじゃないの?」
「なるほど」
それは、何というか。
うっかりすると衛宮人形紐で吊して、そのまま戦うぬいぐるむセイバーなんてファンシーでファンタジーな光景が展開されたのかも知れないな。
「あ、でもセイシンってニクタイに帰属するから、だんだんと人形よりになっていくかも。シロウの耐魔力ってヒドイから、きっと十分も保たなかったんじゃない?」
――――――ゴッド。
衝撃は二度でも三度でも。さらりとおっそろしい事をイリヤは笑いながら言った。
よかった、本当によかった。彼処で軽々しく頷かなくて――――――!
それから、ゆっくりと階段を下りた。今度はあの時みたいに騒々しくなく、緊張もさほどでもなく、調度品に気を払いながら、本当に豪華なお城の中を堪能した。
それでも、やはり気負っているところがあるのか、何となく渇いた喉をさする。それとなく此方の気配を察したのか、じゃあお茶にしよっか。と、イリヤが言った。断る理由なんて無かったし、歩きずくめは流石に疲れる。ひょっとしたら俺、観光旅行なんかは向いていないのかも知れない。
「エミヤ様」
「あ、ええと、ありがとう」
セラが入れてくれた紅茶に口を付ける、うん、こりゃ本当に美味しい。
「凄いな、これ、遠坂の淹れたヤツよりも上手いんじゃないのか」
「当然です、私どもの勤めですから」
と、素っ気なくすまし顔でさらりと流すセラを。
「ウソ、セラ、てれてる」
敵は後ろにいる物だとばかりに、リズがばっさり切り捨てた。
「な―――! なななな!リーゼリット!」
…………どうやら此方が思っているほど、内心クールって訳でも無いらしい。
…………うん、そう考えてみると、意外に根に持つ辺りとか、激昂すると手が付けられない感じを見せる辺りとか、色々と腑に落ちる。
なにやらまだ言いたそうなセラから目を逸らすと。幸せそうにくつろぐセイバーを、そっと盗み見た。
どういう訳か、彼女はイリヤを見つめていて、その横顔が、幸せそうな微笑みの割には、影が差しているように見えて。
上の空のまま、訊ねていた。
「セイバーはさ」
「はい」
彼女も、何処か上の空のままで。
「オヤジのサーヴァントだったんだよな」
ぱちりとイリヤに緊張が走る。だが、それも一瞬、聞き流すかのように、彼女はリズと戯れていて。
「そうです」
確かな声で、セイバーは返事をした。それが、どういう意味を持つか、今の彼女は理解しないままに。
「オヤジはさ、アインツベルンに雇われてたんだっけ」
「はい、詳しい経緯は知りませんが、アイリスフィールの夫として、切嗣はかの城に居りました」
「じゃあさ、イリヤも知ってるのか?」
「そうですね、窓から、時折見ていました」
「そっか」
「はい」
「気が付かなかった?」
「ええ、私達サーヴァントは、召還される折に世界から知識を与えられます。過ぎ去った年月を省みれば、あの当時の姿のままとは、考えがたいでしょう」
「そっか」
「はい」
会話はそれきりだった。いつもと同じように、引き出しを仕舞ってしまったかのように、その子のことをセイバーは覚えていないのだろう。
「あ、まずいな」
そろそろ日が暮れてしまう。いい加減帰らなくては、藤ねぇに外泊の理由をしつこくたずねられてしまう。
「ダイジョウブよ、シロウ。タイガには城に泊まるって言っておくから」
「え、それは助かる、けど」
行ってみたい場所もまだあるのだ、そこでどうなるかは解らないが、とても大切な記憶が彼処にはあって。
「俺、そろそろ行かなきゃ」
夜の森は暗い。それにこの季節だ。あまり遅くなるのもどうかと思うし、かといって日中に行きたい場所かと言えば、そんな事もないし。
っていうかだな。
日中に何て、とてもではないけど正気じゃ行けそうにない。
「うん、だから、ダイジョウブ」
「んん?」
いやさ、そこはホラ。イリヤが平気でも俺が平気でないっちゅーかなんというか。
「シロウのにぶちーん、ワタシが言い訳しておくからって言ってるの!」
そんな俺に苛立ったのか、だーっと両手で俺の頭をべしべしやりながらイリヤがぶっちゃけた。
「――――――おぉ」
納得するまでに、我ながらえらく時間が掛かったなぁ。
「シロウ、場所は判る?」
「ん―――何とか」
見渡せば遠く、必死で走った道を体が覚えていた。そちらの方向に視線を向けるだけで、セイバーが身構える。歩きにくそうにしているのは、なれない靴を履いているためだと思う。どうしてよりにもよって革靴なのか。
いや、その格好には似合っているから、町中にいる分には良いと思うのだが。
「イリヤ、ありがとう」
此処まででいいから、と、声をかけ、森に向かって歩き出した。それは、何時かの夜と同じ。ただ、今日は遠坂がいない。誰一人として、犠牲になる者も。
「朝になったら、来た場所に車を用意しておくから、セラの運転よ。帰りはそれに乗っていって」
「わかった」
「あと、これ、セラから」
「ん、お、サンドイッチ。ありがとうって伝えてくれるか」
「自分で言ってくればいいじゃない」
「そっか、そだな。じゃあ、明日あったときにでも」
城の入り口に向かって歩いていくイリヤと、大きな声で言い交わす。それは、何時かの夜と違う。今日、胸にあるのは、何処までも暖かい感情だけだと言うことだろうか。
再び茂みに分け入った。
「ぬあ、なんだこの、くそ。行きよりも藪がからみついて仕方がないぞ」
「だから言ったではありませんか、剣を持って行かないのは愚か者の所行だと」
咎めるように、セイバーが口を開く。
「ぐむ――――――」
返す言葉がなかった。この状況下においては、確かに理が通っている。藪を払うぐらいなら、あれ一振り在ればずいぶんと違うだろう。彼女が他に携帯していた大型のサクスだけでも状況はがらりと変わっていたと思う。
でもそんな意見が町中で通用すると思うなよ、常識って奴を嘗めたらえらい目にあうんだ。
しばらくうだうだと考えて、結局の所、セイバーが文句を言うのは、俺が歩きにくそうにしているからだと結論づける。
よし、上等。
去年と同じように、何処までも突っ走ってやる。
「セイバー」
顔を上げた彼女を抱え上げた。
「え、え!? な、何を――――――」
わたわたと抵抗するセイバーの腕をうまくかわし、息を大きく一つ。
「喋ると舌噛むぞ」
「――――――〜〜〜〜ッ!!」
用意ドン、走る先にある事なんて、とりあえず考えなくても良いだろう。休憩場所は、あの廃墟でも問題あるまい。
息を荒くすることはない、軽く弾む程度に、何て悠長なレベルでもない。死にものぐるいとは言わないまでも、在る程度の必死さで森の中を駆け抜けた。
「シロ、ウ! 何も其処までしなくても!」
がくがくと揺れる視界の中で、セイバーが必死に声を絞り出す。
はは、平気平気。この程度でも何かの切っ掛けになるのなら幾らでもやってやる。俺の体力なんて二の次三の次だ。
落ち葉を踏み越え、倒木をまたぎ、枝をかいくぐって一頭のケモノになる。流れていく視界を判別することはない、そんな余計があったら胸の彼女を感じていたかった。
全力。必死で走るのはとても楽しいことだと思う。枝に倒木、生え茂る木々も、見ようと思えば大した障害物になり得ない。去年はさんざん走り込んだのだ、この程度、平地を走っているような物だ。危機感の無さにちょっと物足り無さを感じつつも、力を出し切る爽快感にかまけて走る。
しばらくして集落の後に入ったのか。視界の端に、崩れかけた煉瓦の壁が見え隠れしてくる。幾つもの廃墟が、森の中に点在している。木々と一体になった煉瓦の建物群は、どこか幻想的で良い。どうにもこうにも、廃墟というのは人を引きつける何かがあると思う。
と、不意に視界が開けた。いつかの夜、命がけで逃げ込んだ建物。大きく息を一つついて、セイバーを地面に下ろす。あの時は必死すぎて見えていなかったが、思ったよりも、城から近い所に在ったようだ。
こうして落ち着いてみると、弓兵が稼いだ時間がどれほどの物かよくわかる。バーサーカーが動き出して俺達に追いつくまでは一時間も無かったと思う。迎撃に適した場所を探し出すのにも、それ程の時間はなかった訳だ。あの化け物相手に一晩、本当に何者だったんだろうか。
「セイバー、ちょっと休憩」
「え、その……他にしませんか?」
「なんでさ」
中に入ろうとする袖が引かれる。踏み出す力を妨げるほどには強くないが、心を置き留めるにはほどよい力具合。
「此処には何もない、行きましょうシロウ。何もないのだから」
「え、なんでさ。此処で何もなかったなんて事はない。とにかく入ろう」
そう言って、彼女の手を引いた。観念したかのように、うつむいたままセイバーは従った。
うーむ、なんだか無理矢理連れ込んでいるみたいで気が引ける。行ったことこそ無いけれど、ラブホテルの前でもめてるカップルはこんな気分なのかも知れない。
既に日は落ちかかっていて、当然の如く灯りのない部屋の中は暗い、今しばらくすれば月明かりに照らし出されるのやも知れないが、今はまだ、彼女の顔色すらも見て取れなかった。
去年と同じ、まるで、時が止まったままの様な光景に意識だけが時間旅行。居ないはずのもう一人が、階段を一段飛ばしに駆け上がっていく。頭を振ってそれを追い出した。だって仕方がない。アイツの事を此処で思い出すと、そこから先のどうしようもない記憶まで引き出されてしまって困る。
相変わらず一階は木々が床をぶちこわしていて、半ば森と同化している。腰に手を当てて、溜息を吐いた。やっぱり無理、ここに入った以上は思い出してしまうしかない。だって、その、何というか。覚悟が要るのは俺も同じで、見上げるだけで息が詰まりそう。二階の部屋には、赤面するしかないような記憶が刻まれている。
ざりざりと砂埃の積もった、うっかりすると抜け落ちそうな石の階段を上る。所々から木々の芽が吹き出している辺りが何とも言えずシュールだ。本当に此処が日本なのか怪しくなる様な、石造りの家。登り切った其処には――――――
「――――――」
――――――息をする音すらも耳障り。
森の静寂の中に、時間が止まったままの部屋が取り残されている。
空気こそ窓から微かに流れているものの、ベッドはそのまま残っていた。シーツの僅かな乱れが、否応なしにあの夜のことを思い出させて赤面させる。嵐が幾度も直撃したはずだった。風の強い日もあった。だというのに、この部屋はあの時後にしたままどこもかしこも変わっていなくて。
なんともいたたまれない気分、頬を掻きながら腰を下ろした。軋むベッドに、体液の後はない。セイバーから溢れたそれは、全てが魔力となって立ち消えたのか。ああ、その、自分でも何を考えているのやらと真剣に思う。
ふ、と、セイバーを見ると、なにやら居心地が悪そうに階段の向こうからこちらを伺っている。――――うむ、だんだんと俺も居心地が悪くなってきた。男女が二人でえんえんベッドを見つめているなんて不健全だ。いやさ、健全と言えば健全なのだが、それをなにもせずにそのまま見ているとかああもう何を考えているのやら。再び袖を引かれる感覚に目を落とした。軋む階段を上って来たセイバーが、先程とは少し違うニュアンスで袖を引いている。
彼女の顔を見ると、そこはかとなく紅い気がする。
「なにか思い出した?」
と、掠れた馬鹿な事を聞いた。
「特にはありませんが、おかしな気分です」
と、上擦った声でもっと頭の悪い答えが返ってきた。
ああくそ、これ以上此処にいたら、歯止めがきかなくなりそうで困る。近くに来たセイバーの息が少し荒かった。落ち着いた俺の息まで荒くなりそうで堪えた。
けど。
きっとそれも越えて、俺達は。
「それで、どうするのですか」
「うん、日も落ちたし、今夜は此処で」
「そうですか。では」
「そう、そのバスケット」
走っている間、彼女が大事に抱えていたバスケットから中身を取り出していく。小洒落た小さな籠に、幾種類もの具材を使用したサンドイッチが詰め込まれていた。
うむ、お見事。これは負けていられない。
会話はない。ただ、ゆっくりと時間が流れていく。緩やかに通り過ぎていくそれらは、何もかもを浚っていく抗いようのない流れだ。
月が昇ったのか。夕闇から夜の暗さへ。それから、月明かりの青白さに部屋の中が移り変わっていく。かたかたと風になる窓を閉じて、それだけでずいぶんと温もりが違う。持ってきた懐炉を彼女に渡して、ベッドから降りて床の上にごろりと寝ころんだ。
天井は煤けて暗く見えない。何かが潜んで居るんじゃないか、みたいな事を考えさせる空間がある。きっと妖怪。そんな神秘が、昔はそこかしこに存在していて。
何時かの夜と同じように、彼女は窓際で月を眺めている。思いの外明るいそれが、白々と彼女を照らし出している。スポットライトの下で笑う歌姫のように。切り取られた四角、こぼれ落ちる月光に照らし出されたその姿は。
「――――――ぁ」
そうだ、あの夜も。
雲間から差した月明かりに照らされて。明かり取りの窓から差し込んだ光は、碧く透明で。
“――――――問おう”
ああ、覚えているとも。剣戟のきな臭さすら押し流す清廉な空気。エメラルドみたいな瞳はまっすぐで。
殺されかけた俺が、言葉を発するまでもなくて。
“貴方が、私のマスターだろうか”
――――――そんな、かつて聞いた、今となっては懐かしい音を聞いた。
「セイバー」
「はい、何でしょう――――――ッ」
振り返った彼女の顔が痛みに歪む。
そのまま、頭を抱えて床に。とっさに踏み出して倒れ込む体を抱き留める。
「は、ぁ――――――?、?」
「セイバー!?」
「あ、ああ、――――――ぅ、ぐ」
「しっかり、くそ、何が――――――」
様子は尋常じゃない。
頭が、痛むのか。己の頭を握り潰さんとばかりにセイバーは指に力を入れる。彼女の細い指がぎしぎしと力に軋み、もう一方の手は何かを求めて中空を彷徨う。頬に触れた、縋り付くような爪に力はない。それでも、美しい形のそれはひっかくだけで赤く跡を付けていく。頬から顎、飛んで、シャツの襟元。ぎゅっと握られた。とっかかりを捜していたのか。其処を支点にして彼女は自らを引き寄せる。
丁度俺の腕の中。そこに、抱き寄せられる形で。
言葉はない。ただ、震える彼女を抱えている。
〜To be continued.〜
メールフォームです。
dora様への御感想はこちらからどうぞ!!→メールフォーム
dora様の寄稿なさっておられるHPはこちら!

戻る
玄関へ戻る