「私は貴女を信じられなかった」
呻くように彼女は言った。紅茶を口に運びながら彼女は言った。
「そうね、ちょっと傷ついたかも。もう家には置けないわね」
切り捨てるように言う声とは裏腹に、その表情はひどく優しげで。
「だからセイバー、今日からは貴女が信じられる人の家に行きなさい」
開け放たれた窓からは、少し冷たい二月の風が吹き込んできている。坂道の遙か下からは海の風が、遠い山並みからは山の風が。入り交じったそれは、ひどく力強くて。
「私に出来ることは此処までよ、後は、貴女自身でどうにかしないとね」
トーストを囓りながら遠坂が言う。何でもない、いつもと同じ朝の情景。眠りから覚める直前の空気にも似た。
時刻は十一時過ぎ、日差しはいよいよ暖かく、見えてすら居なかった春の気配を感じさせている。途中、間桐の家を通り過ぎる。ばったり桜と出会すかも知れないと思ったが、昼間の屋敷はいつもと同じように静まりかえっていた。何となく不気味さすら感じさせるたたずまいは、まるで其処だけがこの街の異界のようで。と、ああ、そんなことを考えちゃいけない。なんて思いながら、もう一度視線を投げる。違和感こそ付きまとう物の、慎二が魔術を学んでいたって言うぐらいだから、それぐらいは仕方がないだろう。それをいうならば、遠坂の屋敷だって似たような物だ。幽霊屋敷呼ばわりされている庭深い屋敷に比べたら、柵も何もなく玄関まで素通しの間桐邸の方が余程開かれている。いや、それでこれだけの違和感を感じるのだから、それなりに警戒はしているのかも知れない。まあでも、暗いとか考えるのはよそう。いくらなんでもそれは、桜の住んでいる家に対して失礼ってもんだろう。
ふと、甘い空気を感じて振り返る。熟柿のような、地に落ちた果物のような。其処には一人の老人が立っていた。見かけたことのない人物だ。細く枯れ木のような体を和服で包んだ老爺は、炯々と光る目で此方を一度強く見つめると、口の端を持ち上げて屋敷の中に消えていった。声をかける暇もない。察するにあれが、藤ねぇの話に出てきた間桐のご隠居だろうか?
扉が閉まる頃に、セイバーが鋭く振り返った。なにやら緊張した様子だが、何事もないことを告げると不承不承歩み始める。
昨夜の一件以来、彼女の、セイバーの動きというか距離感が何処かあやふやだ。俺達に対して、どうやって接すればよいのかで心の揺れを隠しきれない様子。遠坂には怪我の件を伏せたが、シーツに付いた血の染みを見て、一度だけ彼女も鋭く瞳を絞った。互いに何も言わないところをみて察してくれたのだろう。短く視線をよこすと、それ以上は何も言わずにシーツをゴミ箱に叩き込んだ。それから、申し訳ないとうなだれるセイバーの頭を上からスパーンと景気よくひっぱたいて、「よし、反省しているのならこれで終わり、今のはシーツの代金代わりよ」だなんて、頭を押さえて目を白黒させるセイバーそっちのけで言ってのけた姿はめったやたらと格好良かった。
時折後ろを見て、セイバーの姿を確認しながら、さらに坂道を下っていく。もうじき十字路に出る、そこから先は、取り敢えずまたバスだろうか。風に吹かれる枝を見て、あ、この先は風が強そうだ、なんてことを考えながら持ち上げた視線に、見覚えのある人影が映った。思った通り風は強いらしい。透き通るような銀色の髪が、風になびいている。時折身を縮める様が、ひどく寒そうに思わせた。こちらにはまだ気がついていないのか、退屈そうにガードレールに腰掛けて、脚をぶらつかせている。
当たりに人影はない。虎は、まず無いだろうが、セラとリズならどっちか付いていそうなものだが……一人で来たのだろうか、様子から察するに、誰かを待っているみたいだけど。幾ら鈍いとはいえ、それが自分であることぐらいは察しが付く。とにかく、無視して通り抜けるわけにも行くまい。そもそもからして家族の横を素通りなんて、できっこない。
「おーい、イリヤー」
声に誰かを知ったのだろう。待ちかねた様に一度小さく溜息を吐くと、銀色の少女は帽子を被り直し、居住まいを正して唇に微笑みを乗せた。なんだかそれはとっても良い笑顔で。ガードレールから離れて、こちらに歩いてくる。寒いところの出身だが、寒いのは嫌いと言う彼女は今日も着ぶくれている。ダウンの短いコートがよく似合っていて愛らしい。
「何してるんだ? こんな所で」
…………幾ら暖かい冬木とはいえ、二月の風はまだ幾分冷たい。うっかりすると、雪だって降る。珍しい事には違いないが、去年はあった訳だし。身震いした。さっきまでと違って建物の陰に入ったせいか、なおさら吹き付けるそれが冷たく感じる。もう一度、少しだけ身を震わせて襟を寄せる。いやけっこー寒いぞ此処。息の色の濃さも、急に増したように思える。イリヤが風邪を引かないか、心配になりそうなくらいだ。
「ワタシ? シロウを待っていたの」
白くけぶる息を吐きながら、イリヤが言った。静かに立ち上ったそれは、すぐさま風に吹き消されて。にっこりと笑うと、彼女は俺の腕にいつもと同じようにしがみついた。
「俺?」
ん、と小さく一つ頷いて。それから、それからゆっくりと俺から、俺の後ろへと視線を流していく。その先に居るのは勿論、セイバーだけで。振り返った視線の先で、ひどく狼狽する彼女。最初にむっとして、次に、はっとして、最後に視線を泳がせた。
「本当に驚いたわ――――タイガがね、シロウがおかしいって調べようとするのよ、フジムラの人間ソウドウインで。押さえるの、大変だったんだから」
「む、それ、凄く助かった。けど、いずれ知られる事じゃないか?」
「シロウは自分で言いたいでしょ?」
ああ、うん、それは確かに。此方の表情を見て、納得したと思ったのだろう。悪戯な顔でイリヤは笑っている。
「じゃあどう言うの?」
「ありがとうイリヤ、助かった」
「いいわ」
セイバー、と、微かな、本当に微かな声で呟くと。俺の腕を放して、セイバーの正面にイリヤが歩み寄る。驚きと猫のような好奇心。諦観にも似た喜び。それから、複雑ないろいろなそれ。瞳に揺れる感情は、とてもじゃないが計り知れなかった。
「リンから話は聞いているわ。――――――セイバー、私はイリヤスフィール・フォン・アインツベルン。ごきげんよう、お久しぶり」
スカートの端を行儀良くつまむと、イリヤは何時かした夜の挨拶のように、おしゃまに頭を下げて見せた。
「――――――貴女は」
何か。
何か記憶が刺激されるのか。セイバーの肩に力が入る。緊張したのは俺も同じだった。視線を下ろすと、我知らず脇腹に手が添えられている。微かに痛みを思い出して顔をしかめた。ああ、この感覚はよく覚えているとも。なんせ、ぶちまけられたのは俺の中身だし。
あの時感じた恐怖を。
絶望と言い換えられるような黒い巨体を。
彼女が思い出してしまったとしても、それは仕方のないことだと思う。
「セイバー」
手で触れることはない、緊張した彼女にそんなことをするのは、心臓にも悪いだろう。添うように横に立って、声を掛けた。
額を抑えるセイバーの顔が、歪む。
まるで頭痛に耐えるような仕草、何も出来ないことが、歯がゆくて仕方がない。
僅かな沈黙の後。イリヤに促されて角の先に止められていた車を指し示した。
「思ったよりも遅かったから冷えちゃった。さ、乗って」
と、ベンツェのドアをこつこつとつつきながら言う。どうやら気を回してくれているらしいが、肝心の俺はどう回っているのかがさっぱり解らない。
「え、そのイリヤは遠坂から」
「そ、電話貰ったの。話は聞いたから後は任せて」
それだけを短く言うと彼女は、二人を後部座席に押し込める。運転は誰がするのかなんて訊ねる閑もないぐらい、一応見渡してもそれらしい人影は――――って、ちょっと待て。困惑する此方の思惑なんて知った事じゃないとばかりに自分はさっさと運転席に乗り込み――――
「え、イリヤ!?」
「じゃ、行くわ」
――――――こちらが戸惑うの何処吹く風と、スムーズな操作で車をスタートさせた。スムーズなのは其処までだった。
「微睡みの終わり」
Presented by dora 2007 02 27
改稿 2007 03 11
〜Interlude in 2-9〜
視界がクラッシュする。
雑音と砂嵐。ブリテンには存在しなかったノイズと、吹き荒れる吹雪。カタカタと鳴る機械、ファクシミリとキーボード。冷たく重い冬の城、そして柔らかな笑顔を浮かべる二人の姿。ひどくせっぱ詰まったカタチ、不自然なくせに溶け込んだ世界。吹雪の結界に守られた空間は異界法則の一歩手前で。
かけられた言葉は少ない、突き刺すようなそれだけが渡された全て。磨き抜かれたと言うには少々の違和。錆び付いて、軋む歯車のような、鋼のように頑なな男と、雪の精の様な幼子の姿。見たことがあるようで全くない様式の部屋、与えられた食事は暖かく――――――ひどく温もりとは遠い。
頭が痛む。
雪が止めば遠く窓から見える胡桃の林、私が願った楽園の影も見えず、其処にはただ厳しさだけが在る。春の気配など、何処にもない。穏やかに流れる小川もなければ、林檎の林もない。並び立つ木々は、暗い葉の針葉樹と冬枯れたウォールナットのそれで。
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン。確かに自分はその名を知っていた。アイリスフィールというのは、誰の名前だったか。
頭が痛む。
血の臭いがしたと思う。サイカイは突然で、昨日別れた幼子が今は少女として在る。あれから相当な時間が経っている。その時間がどれだけの長さなのか私には解らない。ただ赤く燃え上がる町の中で、少年の心を殺して青年に至る道を開いて、父親の絶望を幼子に知らしめるために二度の現界を果たして。見覚えのない、だが、良く憶えている赤い瞳。何よりも強烈な死の気配を引き連れた赤い瞳。かの二人が願っていたのは、そんな未来では無かったというのに。
かつては声を掛ける暇もなかった。かけたところで、彼女がそれを憶えているとも思えない。聡明だとは思っていた。だが、話したことは――――――あっただろうか。
そも、今の己が確たる物として捉えられないのに、不確かな記憶に頼るのはいかがな物か。
アタマガイタイ。
頭痛はいよいよ激しさを増し、視界に吹き荒れる砂嵐は遠い話に聞く砂漠のそれのよう。ただ――――――バックミラーに映る赤い瞳だけがとてもクリアーで。
「貴方、は」
沸き上がる違和感に吐き気が持ち上がる。握りつぶすような心持ちで額を掴むと、押し殺された声が口から漏れた。己が己でない、王が誰かの下につくことなどあり得ないと言うのに。この身には二度も誰かの騎士として仕えた記憶が残っている。
不意に、鏡の中の瞳と目があった。
身が震えるような恐怖と懐かしさ、確かに感じていた、教え子を見るのにも煮た愛情。慈しむ心。突然沸き上がった訳のわからない感情が、平静を装う貌を歪ませる。
「憶えてる? 私のこと」
鼓膜に突き立つ声はすずやかで、確かに聞き覚えがあると感じている。
だが、違う。
それでも違うと思う。
同じ声なのに。彼女とまるで同じ声。彼女よりは幼い声。だが、あまりにも同じ魂の輝きに私の目は痛んで仕方がない。まるで夢の中の記憶、否、夢の記憶であることに間違いはない。困惑するのはそのためだ。私は一度もそんなことをした憶えがないのに、この魂に刻まれている記憶がある。
どれほどそれを見続けただろうか。死に至る微睡みの中、幾度となく繰り返し見た夢の数々。幾たびも聖杯に手を伸ばし、幾たびもそれを阻まれてきた記録。何処で、誰と。誰を殺して誰を助けて。誰と共に歩いて。誰を、愛したのだったか。
解らない。私は女ではない。性別が女であっても、私は女であることを捨てた。あの日あの剣の前に全てを置き去りにして、だって言うのにこの身は誰かに抱かれたそれを記録している。肌の温もり、髪の匂い、荒い息と青臭い精の匂い。端的に言えば、全てを憶えている。だが、それが何処に入っているのか判らないだけ。あちらこちらにしまい込んだ宝物、その全てが何処にあるのか、何を持っているのかを私は無くしている。
剣。それが私を指し示す記号。戦う、それが存在理由。目的はただ聖杯の為に、私は無限の繰り返しの中を彷徨い続ける。願い、ブリテンに相応しい王は何処に。誰ならば、あの悲劇を止められるのか。誰にも止められない。私には出来ない。彼にも出来ない。誰にも出来ない。出来ない出来ない出来ない出来ない。不可能。そんな、悲しい結論。
だが不思議だ。それが不思議だ。誰も誰もを助けられないと知って、それを胸に抱いて、答えと知って暗い階段を上った。温もりは唇に、優しさと暖かさに包まれて、最期の時を迎えるために。剣は戦いに赴くのだ。私を納める鞘と共に。
暗い十字架、あふれ出る泥、緩やかに降りてくる少女は何一つ身に纏わず。聖杯、それがあんなに汚らわしい物だとは知らなくて。私は焼き尽くすしかなかった。一度ならず、二度までも。だが、それで良かったはずだ。あれは破壊しかもたらさないと知った。だからもしもアレに願ってしまったのなら、何もかもが焼き尽くされて、灰燼に帰したブリテンに一人立ちつくす羽目になる。
御免だ。命と引き替えにしてもダメだ。そんな事をしてしまったら、今度こそ私は私を許せない。サーヴァント7体を組み込んで、正しく根源へと通じたあの穴ならばまだどうにか出来たかも知れないが、私は。私は――――――
――――――セイバー、その責務を果たしてくれ。
少年の祈り、己よりも短くしか生きていない愛しい者の誓。私が何よりも大切だと言ってくれて、私の全てを肯定してくれた貴方。見る者によれば否定にしか見えないそれも、ただ私の間違いを正す松明の光に他ならなくて。
頭痛。激しいそれ、頭蓋が内側から砕けて割れる。辺りに撒き散らされるのは、自分でもどれがどれだか解らない私の部品。幻視した。彼と共に歩いた道を。この車で、彼女と共に走った道を。そうだ、あの時も冷や冷やとさせられっぱなしで、彼女が握るステアリングに冷や汗を掻いた。キャスターとの遭遇は、確かこの先で、この道は、私がライダーと走を競った。我が剣は確かに彼の宝具に打ち勝って。それで、彼が違うのだと納得したのではなかったか。
辿り着いた場所、彼女の居るはずの場所。其処には、彼が居て。憎悪に燃える声を浴びせて、必殺の剣はどれも重たくて。私は、彼に敵う筈など無くて。
いっそうひどい、頭痛、白くて、間隙に何かが滑り込んでくる。巻き戻される記憶。呼び込まれる記録。がちんがちんと打ち合わされる撃鉄は、誰の意識の中で。
バーサーカー、巌の巨人、それとも、黒鎧の騎士か。キャスター、神代の魔女、あるいは、水魔の騎士か。ランサーはいつも同じ、彼らは己の誇りに生きて、己の誇り故に命を落とした。アーチャーはいつもヨクワカラナイ。彼らの考えるところは私には理解できない。ライダー、実は皆まっすぐアサシンは余りにも違いすぎる、そんな中で、私だけが――――――
ばらばらだった。引き出しの中身を、床に全てぶちまけたような惨状。何処に何があるのか判らないから、とりあえず全部をひっくり返して途方に暮れている。前後も左右も、順番が滅茶苦茶で裏表すら定かではない。うやむやになりそうな順序をまとめる努力は、頭痛のせいで無駄になってしまう。そうしてまた盛大にひっくり返された記憶を前に途方に暮れるのか。
「お母様の事、思い出せる?」
それでも、少女の声は容赦なく記憶のパーツを突き付けてくる。それがパズルの何処に填るのかも判らないまま、押しつけられたそれを手に困惑に揺れる。
まるでバケツで水を掛けられる小さな植木鉢。渡される情報が多すぎて、憶えきることの出来ない新米伝令兵。
全てを識っている。
だというのに、何も知らない矛盾。頭の中を剣でかき回されているようだった。
「……何を言っているのだ、貴女は」
それだけ言うのが精一杯。だって思い出す。僅かな間しか見ては居ないが、確かに其処にあった夢の一幕。お母様と呼ばれるだけで、彼女の顔を思い出した。だが――――――肝心の名前が思い出せない。
赤い瞳の少女によく似ている。そのまま健やかに育てば■■■■■■■■の様になるのだろうか。今は若木のようなその肢体が、みずみずしく育つことは――――――無いと知っているのに。
なんて残酷な夢想。むしろ出会えた事が奇跡のようだというのに。
僅かな時間しか保たないと、見知った誰かが言っていた気がする。
鮮やかに赤い、黒い髪の少女。あれは――――――誰だっただろうか。
顔、顔だ。
顔さえ思い出せばもう少しで名前も出てきそうなのに、幾つものパーツが足りなすぎて顔すら思い出すことが出来ない。
アイリスフィール。彼女の顔はどうだったか、私と、私を騎士と呼んでくれた彼女の名は、何だっただろうか。守ろうとして守れなかった彼女、私は、女こそを守れない。いつも、常に。誰一人として。人が人であるように、女も人であるようにと、治世に望んでいたのに。私は女こそを守れない。
「――――――無理しなくて良いわ、隣にシロウが居るのなら、何時か思い出すから」
「――――――」
幾度も呼んだ名だったと思う。思い出せないことがもどかしい、いったいどんな気持ちでその名を呼んでいたのかが思い出せない。はらわたをまき散らして、私の元に滑り込んできた少年。生きていること自体が、■■前の出会いすら奇跡そのものの私の■。
限界を感じていた。脳髄を暴れ回る情報は私を容易く突破し、あらゆる所からあふれ出て乱れている。もう目が見えない。考えることは無理で、何かを見ることも聞くことも出来ない。
一度きつく眼を瞑って、暴れ狂う記憶の濁流に窓を閉じた。何も引き出せないが――――――壊れてしまうよりもマシだとは思う。
そんな私を見て苦く微笑むと、それきり興味を失ったようにイリヤスフィールは運転に意識を戻した。
〜Interlude out〜
国道沿いに、ガードレールのとぎれた箇所があった。具合の良いことに、駐車する程度のスペースはある。滑り込むように車は其処に止まった。見覚えのある場所だった、いつも、タクシーを止めるのもこのスペースで。
「ここからは歩きよ」
「イリヤは平気なのか?」
「なれてるもの」
車から降りて見ると、其処には見慣れた「私有地」の看板が突き刺さっていた。だが通常のそれとは違い、やたらめったら非常にシュールで仕方がない。だって見てみろよ。大木に木製の看板、無論柄ですら木製の根本が突き立っている様は、誰彼問わず此処に立ち入ることを躊躇わせるだろう。一見すると枝にくくりつけたようにも見えるが、明らかにその枝は人工物なのだ、こう、ぐさっと。
っていうか。
これやったの、間違いなくバーサーカーだよなぁ。いったいいつ、いやさ……本気であれにそんなことさせたのか?
「シロウ、それ誰がやったと思う?」
「バーサーカー」
「ハズレ、それね、リズがやったんだよ」
――――――なにそのもっと驚愕の事実。
道案内もなく、イリヤは森の中を歩いていく。倒木を越えるときも、藪を潜るときも、その体からは一切の危うさが見えなかった。まるでなれた道を行く猫の様で。
「む――――――シロウ、今変なこと考えなかった?」
「全然」
ふくれたままこちらを見つめるイリヤに曖昧な顔を向ける。ごまかし切れた自信はなかった。むくれたイリヤの視線を感じながら脚を進める。猫が嫌いな彼女だが、まさか此処まで鋭いとは誰も思わない。これじゃあろくに秘密ももてないな、などと思いながらセイバーを見る。いつしか彼女は横に並んでいた。まるで俺のことをかばうかの様に、僅かに前に出ようとしている。
理由は、自分でもわからないみたいだった。ただ、体がそれを憶えているのか。一歩進むごとに、緊張がセイバーの体を走る。
振り返ったイリヤが、その様を見とがめた。足を止めると腰の後ろで手を組んで眼を瞑る。何かに祈りを捧げるような、別れを告げるような眼差しで言った。歌うような声は微かに震えていて、別れの声を思い出させた。
「何も怖い事なんて無いよ、バーサーカーはシロウとセイバーに殺されちゃったから」
殺された。
怒りもなく、恨みもなく。
ただ悲しみだけが言葉に宿っている。仕方なかったと言うつもりはない、殺そうとして、俺達はアイツに立ち向かった。生き延びたのはこっちで、バーサーカーは剣に朽ちた。
いや、仕方が無く、とか、殺す気で、とか。結局は後でどうこうってレベルの話。幾らかっこつけたところで、事実は変わりようがない。ただ、胸が痛かった。
殺したと言えば。
アイツが、俺が殺した最初の相手。
「……バーサーカー」
どこか呆っとした瞳でセイバーは呟いた。不意に思い出して、彼女の足下を見やる。
「あ、遠坂の奴」
森に行くことを進めていたのに、セイバーが履いているのは茶色の革靴だった。かわいらしいデザインのそれは、間違いなく森を歩くことを念頭に作られてなどいない。硬く、滑りやすい靴底が不安定な彼女を更にかしげさせる。
「――――――ん」
「――――――む」
「…………ふぅん?」
それが危なっかしくて、何を考えるでもなく、セイバーの手を引いた。緊張に、血の気が引いているのか。何時かの橋の上を思い出すぐらい手は冷たかった。
昼間とはいえ、鬱蒼と茂った森は暗い。積み重なった落ち葉が、かさかさとリズミカルになっている。思い出すことは沢山あった、此処を駆け抜けて、此処を必死に抜けて、俺達は。そんなことを考えながら、空に目を向ける。所々倒木のある場所には空が見えていた。ほっと息を吐いて、手に視線を投げる。気持ちに余裕が出来てきたのか、徐々につないだ手が恥ずかしくなってきて――――――滲んだ手の汗に我に返ったのか。しばらくの間、手をひかれるまま歩いていた彼女が、はっと気がついたように振り払う。
「――――――っ!!」
「うお、とと!?」
ちょっとピンチ。まもなく脱出。折り悪く、倒木に乗っかったところだった。突然崩されたバランスに驚いて振り返ると、こちらを見つめながら、セイバーが振り払ったままの姿勢で固まっている。
…………しくじったかな。
そう思った、確かに性急に過ぎたかも知れない。反省しながら彼女の表情を伺う、と。
「セイバー?」
「あ、その――――――少し、驚いたので」
嫌悪でもなく、侮蔑でもなく。
ただ、驚愕の表情だった。何に驚いているのか、此処に驚く物など何一つ無いというのに。己のとった行動が、突発的で在ることを恥じているのか。僅かに顔を赤くすると、セイバーはうつむいたまま黙り込んでしまった。
視界がオーバーラップする。
何時かの夜に歩いたような、固い地面じゃないけれど。
歩きにくそうな彼女の手を、引いて歩いたことがあったっけ。
あの時よりも少し大人になった今なら、邪魔も入らない今なら。
もう少し穏やかに――――――二人で歩けるかも知れない。
「――――――ん」
拒絶されるかも知れないとは思う。だが、やめるわけにも行かないと思う。一度始めた以上は最後までやり通さなければならないと思う。及び腰になる意識を振り切って、もう一度手を差し出した。何か気の利いたことを言おうとしたが、余裕はもう、ここ数日と今の一瞬で使い切ってしまってソールドアウト。仕方がないのでぶっきらぼうに腕を突き出した。
「え……シロウ?」
彼女に向かって手をさしのべる。何かを言おうと思うのだが、言葉は本当に出てこなくて。
「――――――ん!」
終いには、彼女の顔さえ見られなくて困った。
不器用にそっぽを向きながら、ちらりと盗み見た。戸惑う翡翠色の瞳が、俺の顔と手とを交互に行き来する。困ったように、何か尊い物を見るように差し出したその手を見つめると、彼女はおずおずと手を差し出しながら言った。
「…………シロウ、王の手である」
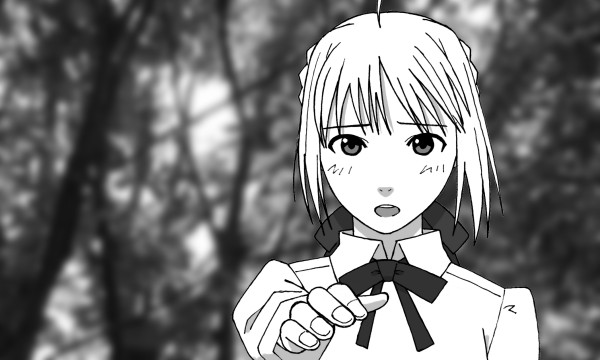
と、どこか自信なさげにセイバーは言った。
「――――――っ」
鼻血を吹きそうだ、その、懐かしい柔らかな響きだけで破裂しそうになる。今と昔が混じり合って混乱する、目の前にいる彼女が誰なのか判らなくなりそうだ。
そのままとっつき歩くセイバーの手を引いて歩いた。呆れたように、少し向こうでイリヤが振り返って笑っていた。
薄暗い森の中を三人で歩いていく。何時かとメンバーこそ違う物の、誰かと行く森はデジャブで気が狂いそうなぐらい。
ふとしたことで目がとまる、あの木の枝は、この倒木は、あの木々の傷は。どれ一つとして憶えがないと思うのに。
忘れているだけの視界に、ちょこちょこ写る記憶の欠片。こぼしていたのは俺も同じで、一つずつ何かを拾い集めていく。優しい記憶も、溢れる怒りも。全てが其処に散らばっていて。
火傷するような、想いの記憶が流れ込んできて仕方がない。俺のも、俺以外のそれも――――
「何処へ行きたい」
と、イリヤが言った。
「何処でも良い」
と、俺は答えた。
「じゃあ、そうね。順番に見て回ろっか」
と、優しい声で、イリヤはセイバーを見つめながら言った。
〜To be continued.〜
メールフォームです。
dora様への御感想はこちらからどうぞ!!→メールフォーム
dora様の寄稿なさっておられるHPはこちら!

戻る
玄関へ戻る